高い原料コストと設備過剰で先行きが危惧された国内石化産業。大手が能力削減を決めた矢先、思わぬ環境変化が…。
この記事は有料会員限定です。
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら

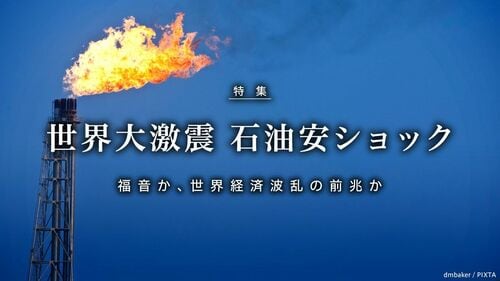


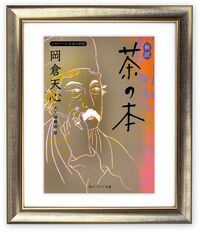


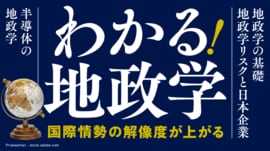





















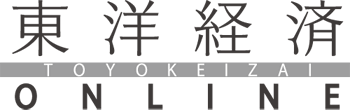


ログインはこちら