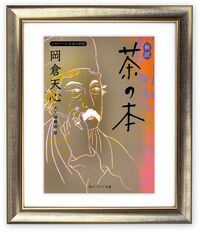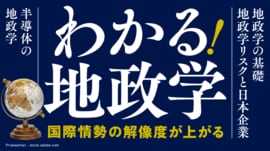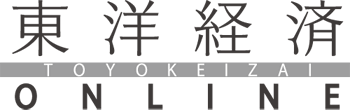デジタル技術が国民の生活へ急速に浸透していく中国。気鋭の研究者と中国ビジネスのレジェンドが、激変する大国の先行きを占う。
デジタル技術の社会実装は中国をどう変えるのか。中国を知り尽くす2人が徹底討論。
(司会 本誌編集長・西村豪太)
──中国のデジタル化への新型コロナウイルスの影響は。
梶谷 オンライン会議の増加や医療分野でのオンラインサービスの普及に拍車がかかり、デジタル化への追い風になった。ただ、コロナ禍がきっかけにはなったが、すでに中国で始まっていたDX(デジタルトランスフォーメーション)の延長線上にあるのだろう。

例えば、スマートフォンアプリの「健康碼(健康コード)」はウイルス感染に対する安全度を判定するが、これはチャットアプリ「微信(ウィーチャット)」や「支付宝(アリペイ)」など既存サービスの情報とひも付けして利用できる。既存のサービスを基にコロナ対策に使われたため、感染拡大への対応が早かったと評価できる。
徳地 デジタル化の流れはさらに加速する。中国社会の需要はまだ満たされていない。中国ではインターネットの利用増加でビジネスチャンスが増えてきたが、これからは「互聯網+(インターネットプラス)」政策の下でネットとリアルが融合していくだろう。また、中国には若くてハングリーな起業家が大量に存在する。さまざまな分野で激しい競争が繰り返され、よいサービスが相次いで生まれている。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待