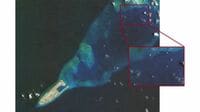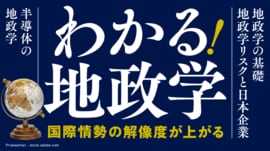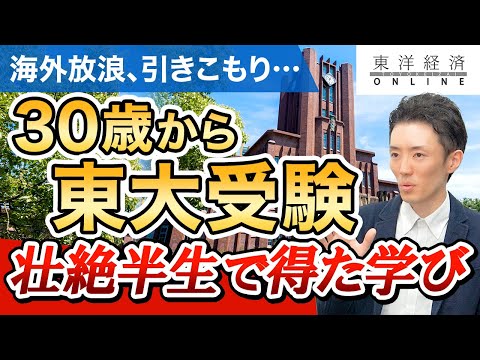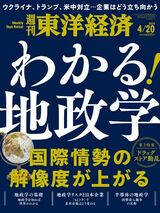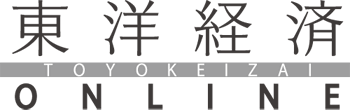──須磨学園はかなり以前からICT教育に力を入れていると聞いています。
私がマイクロソフトにいたこともあり、須磨学園のICTに関してはパソコンが出てきた1980年代から推進してきました。
2000年前後にインターネットが普及してきたが、まずはそれを使った調べ学習を取り入れた。オンライン授業もその頃から試しています。当時はインターネットのスピードが遅く20秒以上の配信ディレーがあった。そういうことは試さないとわからない。一方で、カメラ2台で撮影して、「3Dで授業を配信」といったいろんな試みもしている。でも、「インターネットで授業を配信すること」がコアな部分だということはわかっていたので、それをひたすらターゲットにしました。
──須磨学園ではコロナ禍で、どのようなオンラインの授業対応を行ったのでしょうか。
まず入学式を中継で行いました。さらに始業式や生徒同士の対面式も中継し、その結果を受けて「これは授業もやらないといけない」と大号令をかけた。2、3日で授業を全部インターネットで配信できるようにしました。好評だったが、すべての授業を配信するのは教員への負荷が大きくものすごく大変でした。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け