
かつもと・とおる 1957年生まれ。82年ソニー入社。ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ社長、R&D・メディカル事業担当専務を経て2020年6月から現職。ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ副社長兼務。
2020年5月、金融部門のソニーフィナンシャルホールディングスの完全子会社化を発表し、エレキの位置づけも変えたソニー。グループ事業の再定義を行い、今後どのようなシナジーを見込むのか。研究開発(R&D)担当の勝本徹副社長にテクノロジーの観点からソニーのこれからを聞いた。
7000字のロングインタビューでは、「研究開発で何を加速するのか」「現場から出てきた有望な技術とは?」「ソニーグループの発足でR&Dはどう変わるか」「電気自動車を作った狙い」「ゲームで何を目指すか」「人材獲得の考え方」を詳細に語っている。
(注)本インタビューは週刊東洋経済6月20日号の51ページに掲載したインタビューの拡大版です。
グループの研究開発で何を加速するのか
──現在はどのような形でグループの研究開発(R&D)を進めていますか。ソニーフィナンシャルグループの完全子会社化で、研究開発の融合が進むことになるのでしょうか。
R&Dセンターを私が2018年に担当したとき、吉田(憲一郎)社長から言い渡された要望は「グループ全体にテクノロジーを広げてほしい」ということだった。
それまでは、どちらかというとエレキと半導体のための技術開発がメインだった。吉田社長の要望を受けてから、意識的にエレキや半導体で磨いてきた技術をエンタテインメントや金融に展開する流れを意識してきた。
そのため、実は2年前から融合の動きは進んでいたと言える。(ソニーフィナンシャルが)100%子会社になってそれが加速するという意味合いが強い。R&Dセンターでは大体3~10年くらい先をにらんで開発をしている。
これからは、金融の現場で磨いたテクノロジーをエレキや半導体に転用するという「逆の流れ」が出てくると思う。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
ログイン(会員の方はこちら)
無料会員登録
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら




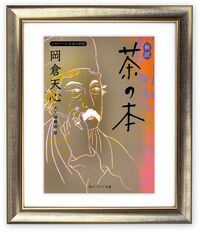


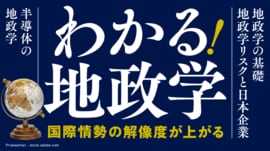





















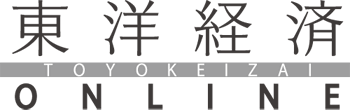


ログインはこちら