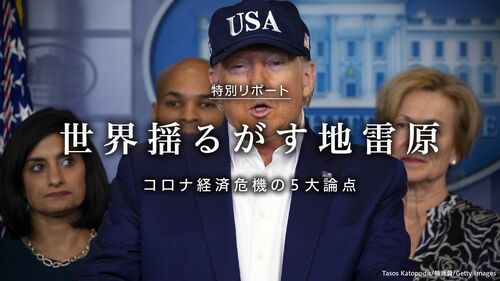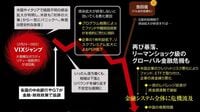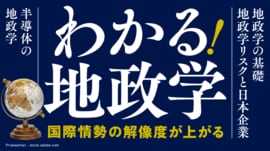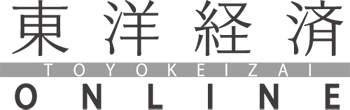「リーマンショック以上の厳しさを覚悟している」 【5000字インタビュー】岸田自民政調会長が激白
✎ 1
✎ 2

コロナショックへの影響を緩和する経済対策が注目されている。考え方について岸田政調会長に聞いた(撮影:尾形文繁)
新型コロナショックの経済影響緩和策を安倍政権に積極的に提言している自民党政務調査会。その要諦を岸田会長に聞いた(取材は3月12日)。
──政府は「先手、先手」と言っているが、「後手、後手」との評価もある。安倍政権の新型コロナウイルス対策をどう評価しているか。
新型コロナウイルスは今、全世界的に大きな懸念として広がっている。発生地である中国だけでなく、韓国、欧州において今爆発的に感染者、死亡者が増えている。その比較においてわが国では、感染者は3月11日時点で550名、亡くなられた方は12名。諸外国の状況と比較すると、わが国の対応は評価できるのではないか。
ただ、コロナ対策にはいろいろなものがある。水際対策、感染拡大対策、そして経済対策。それぞれどう取り組むのか、どう評価するのか、分けて考えていかなければいけないと思う。
水際対策については、わが国は中国に5回もチャーター便を送った。これはほかの国と比べても特筆すべき取り組みだった。感染拡大防止についても、さまざまな取り組みが行われてきた。ただしクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応は国際的にも注目され、さまざまな議論になったところだ。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
ログイン(会員の方はこちら)
無料会員登録
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け
この記事の特集
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら