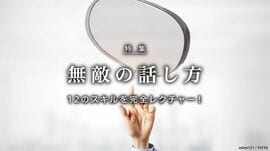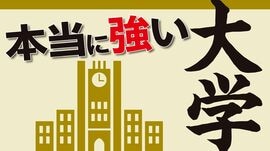知られざる欧州の戦後、ほぼ5年“戦中”だった
評者 法政大学名誉教授 川成 洋
前世紀の2度の大戦を欧州では、合わせて「欧州30年戦争」と呼ぶ。第1次大戦後、英、仏による宿敵ドイツと社会主義国家ソ連の封じ込めを主眼とする戦後処理が第2次大戦を誘発する大きな要因の1つだったからである。
ヒトラーの死をもって欧州での第2次大戦は終結したが、終戦とともに欧州は復活の道を歩み始めたのだろうか。それともドイツ古典派詩人シラーが嘆息したように「戦争は戦争を養」ったのだろうか。
本書は、終戦直後から1940年代末までの5年間、欧州全域に吹き荒れた復讐の情念が引き起こした途方もない残虐行為を、被害者から子孫への口伝も用いながら、実証的に詳らかにしている。厚さ故か、価格故か、大メディアに書評がないが、間違いなく必読の名著である。
ドイツの戦争捕虜は1100万人を超え、さらにドイツ軍の占領地にはほぼ同数のドイツ人が居住していた。彼らはナチ時代の加害行為の実行者として憎悪の的となり、本国に送還される権利は認められず、暴力的に国外追放となった。ドイツの版図も、領土不拡大や民族自決をうたった41年8月の大西洋憲章とは裏腹に、大幅に縮小された。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待