世界の針路を129テーマで徹底解説 2019 大予測
絶頂期から停滞期へ 平成30年間ニッポンの足跡
あと4カ月で平成という時代が幕を下ろす。
振り返れば平成は絶頂から始まった。平成元年(1989年)12月、日経平均株価は3万8915円の史上最高値を記録。まさにバブル景気の絶頂期だった。地価は高騰、世間はディスコやスキーのブームに沸いた。
ちょうどその頃、世界は大転換期にあった。89年、ベルリンの壁が崩壊。同年、米国のブッシュ大統領と旧ソ連のゴルバチョフ最高会議議長がマルタ島で冷戦終結を宣言し、91年にはソ連が崩壊。一連の国際政治の動きは“グローバル化”時代の幕開けを意味していた。日本企業は台頭するアジア勢などとの熾烈な国際競争を強いられた。
バブル絶頂と冷戦終結だけでなく、平成の初頭にもう一つ象徴的な時代の変化があった。インターネットの台頭である。
90年代前半、米国はアル・ゴア副大統領の下で「情報スーパーハイウェー構想」を開始。全米にコンピュータネットワークを敷設する計画で、インターネット普及の原動力となった。片や日本の製造業はハード製品中心の事業構造から転換が遅れ、その後の競争力低下を招いた。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け


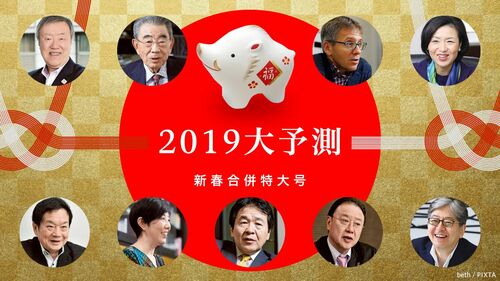






























ログインはこちら