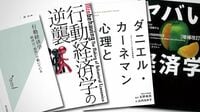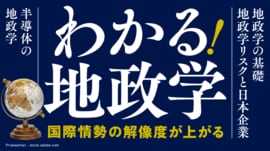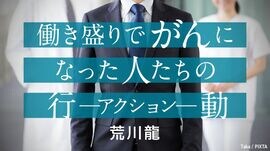根幹を揺るがしかねない政党に対する失望
評者 BNPパリバ証券経済調査本部長 河野龍太郎
高成長がもたらす潤沢な税収の配分を政党が媒介した20世紀後半は、政党政治の黄金時代だった。今や各国とも税収は増えず、高齢化で社会保障費は膨らみ、費用の分担に頭を悩ます。既存政党の支持率は低下し、政党不要論が語られるあり様だ。
本書は、日本の政党政治の行方について、政治学の論客が理論的、歴史的にわかりやすく論じた好著である。

まず、私益を求める政党に一国の政治を委ねるのはなぜか。政党が代表するのは一部の集団の利益でも、複数の政党が有権者からの支持を求めて競争することが、全体の利益につながる。単一政党で一つの価値観に染まった社会は、一見強力に思えても、大きなショックに対して脆弱だ。
野党が支持を失い、自民党内の派閥間での疑似政権交代の復活で十分と考える人も増えている。しかし、政権が一党で固定化すると、利益を享受する集団も固定化される。その弊害を強く懸念したから、政権交代を可能とすべく、我々は1990年代以降、選挙制度と執政制度の改革に着手した。現政権がTPPへの参加を決定したのも、下野の経験で利益集団との間に一定の距離が生まれたからだろう。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待