AIやロボットの台頭で将来の医療はどうなる? 20歳代後半〜30歳代後半の現役医師4人に赤裸々に語ってもらった。
医学部に来年入学する学生は、留年や休学をしなければ2025年にも卒業する。卒業から25年後の50年、バリバリ活躍している頃に、自ら選んだ診療科が廃れていてはあまりにも不幸だ。AI(人工知能)やロボットの開発が日進月歩で進む中、どの診療科に進んだらいいのか、これから医師になる若者の心得とは何かを『医療4.0 第4次産業革命時代の医療』(6月刊行)に登場する現役医師4人に聞いた。

──50年の医療はどうなっているでしょうか。まずは、いらなくなりそうな診療科から挙げてもらえますか。
森維久郎医師 「いらなくなる」というのは極端な表現ですが、病理料、放射線科、皮膚科など画像診断が主体の診療科の仕事は一定数、AIに置き換わっていくと思います。すでに画像診断については、AIと医師で同じ精度であるという報告も出てきているし、この流れを止めることはできないと思います。また腎臓内科としても、安定している人工透析患者さんの薬の調整などでも今後AIの役割が大きくなっていくと思います。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待

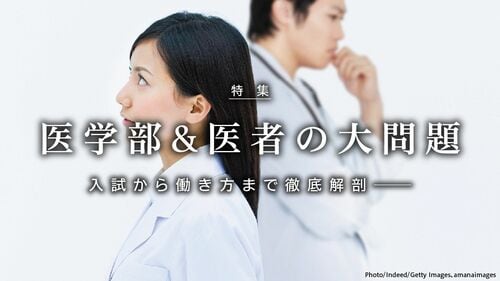



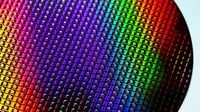



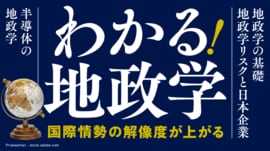



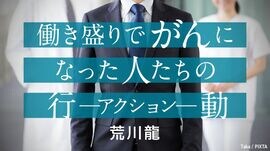


















ログインはこちら