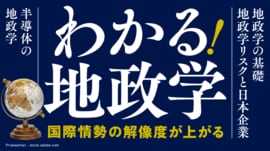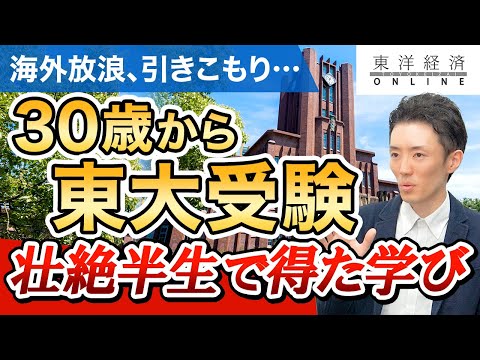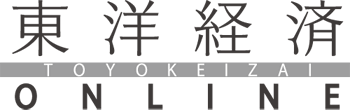こうの・まさる●早稲田大学政治経済学術院教授。1962年生まれ。上智大学法学部卒業。米イェール大学修士。米スタンフォード大学博士(政治学)。加ブリティッシュコロンビア大学助教授、米フーバー研究所ナショナルフェロー、青山学院大学助教授を経る。
方法論と現実のジレンマの中で格闘
評者 中央大学商学部教授 江口匡太
政治学に限らず、社会科学全般にわたり、反証可能な仮説(理論)の提示と、データによる検証が重視されるようになった。データの検証に耐えられたものは生き残る一方、耐えられなかったものは理論の再構成を迫られることになる。説明力の低い理論は修正され、再びデータの検証にさらされる。この繰り返しによって、頑健な理論が構築されていく。この科学的な検証手続きを踏まえていないものは、たとえ重要なテーマを扱っていようと学術業績として認められにくくなった。
科学的な検証は社会科学でも当然必要である。しかし、そこには大きなジレンマがある。反証可能な仮説を提示するのは簡単ではないし、それを立証することはさらに困難である。実験室で自由に実験を設計できる自然科学と違い、地球は一つしかない以上、社会科学は再現可能な実験ができない。その中で厳密な検証手続きにこだわるほど、検証できることは少なくなる。その結果、喫緊の課題であっても、専門的な見解を提示できなくなってしまう。
この記事は有料会員限定です。
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら