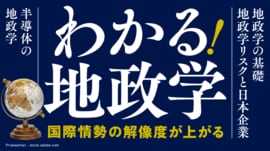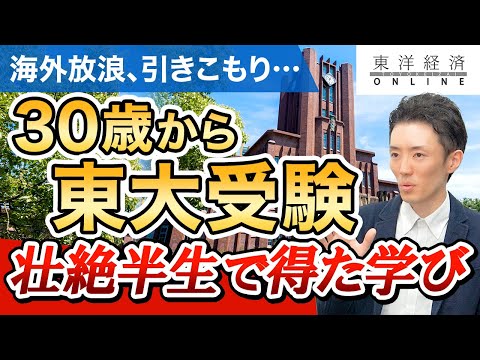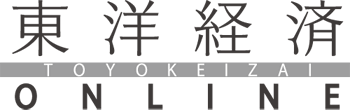これまで来た道を引き返すことを提案
評者 上智大学経済学部准教授 中里 透
7月30〜31日に開催される日本銀行金融政策決定会合では、物価動向に関する集中点検が予定されている。今回の会合では、物価はなぜ上がらないのかが議論の焦点となる見通しだが、本来なら、この5年余の金融政策についての「総括的検証」も併せて行うことが必要であろう。本書はこの作業を行ううえで有益な手がかりを与えてくれる。

2013年4月に量的・質的金融緩和が導入された時、そこには明快なメッセージが込められていた。それは、「物価は貨幣的現象」であり「大胆な金融緩和で家計や企業の期待を動かせば、物価は上がる」というものだ。異次元緩和は円安株高を通じて景気回復と物価上昇をもたらし、14年の春先には上昇率2%の物価安定目標が手に届くところまで近づいたかに見えた。
だが、消費増税後の景気の減速と14年夏からの原油価格の下落があいまって、物価上昇のペースは大幅に鈍化した。こうした状況のもとで、16年2月にはマイナス金利政策が導入され、同年9月には長期金利にも誘導水準を設ける措置が採られることとなった。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待