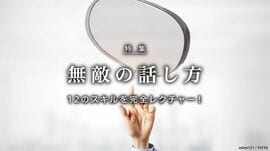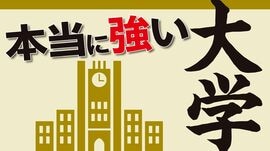不合理な意思決定との結びつきを明瞭に推論
評者 兵庫県立大学大学院客員教授 中沢孝夫
米国との戦争は「高い確率で日本は敗北」することがわかっていたが、それゆえ「低い確率に賭けてリスクを取っても」日米開戦への道を選んだ日本のエスタブリッシュメントたちの葛藤を、通称「秋丸機関」(陸軍省主計課別班)を中心に描いた、見事な歴史資料の読み解きである。
有沢広巳、中山伊知郎、脇村義太郎など、日本を代表する経済学者たちによる日米の国力の客観的な比較と分析は明瞭であり、陸軍もそれを正確に「認識」していた。
にもかかわらず、石油や鉄のスクラップの禁輸など、米国の日本への経済制裁に対して、「2〜3年後には確実に石油が無くなる」という「『事実』(エビデンス)だけに関心が集中し、国際情勢が大きく変化して日本を取り巻く環境が好転するという『ヴィジョン』をもつことは誰もできなかった」と本書は読み解いているが、まさしくそのようであった。
近年の北岡伸一氏などの研究成果(『門戸開放政策と日本』)によれば、戦前の米国の内部にも、米国は日本に勝つだろう、しかしそのあとに登場するのは、もっと厄介なソ連であり中国である、しかも彼らは米国に助けられてもそれに感謝することもないといった見解(米国公使マクマリー・メモランダム)が存在していた。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待