
山田進太郎(やまだ しんたろう)/早稲田大学在学中、楽天でのインターン時にオークションサービス「楽オク」を立ち上げる。卒業後、2001年にウノウを設立。数々のネットサービスを立ち上げ2010年同社を米ゲーム会社・ジンガに売却、2012年ジンガを退社。2013年2月にメルカリ(旧コウゾウ)を創業。(撮影:梅谷秀司)
今日6月19日、メルカリがいよいよ東証マザーズ市場に上場する。国内でフリマ市場の急拡大を牽引してきた流通革命児の新たな“船出”には大きな注目が集まっている。短期的な利益は追わず、「人」「テクノロジー」「海外」に積極的に投資する――。そう明言する同社は、上場の先にどんな成長戦略を描くのか。創業者でCEOの山田進太郎氏に、余すところなく聞いた。
好機は一つも逃したくない
――このタイミングで上場に至った経緯は。
これまでさまざまな資金調達手段を比較検討しながら経営してきたが、サービスの知名度が上がる中で、「社会の公器」になる必要があると感じた。上場企業というステータスを得ることで、年配の男性など顧客層を拡大できる可能性もある。今後、(昨年11月に設立した)子会社の「メルペイ」が決済・金融サービスを始めるうえでは、会社の信頼性を高めることも重要だ。そうした総合的な判断があり、上場の準備を進めてきた。
――昨年は「年内にも上場へ」という報道もありました。金融庁など、関係各所との調整が難航した部分があったのでしょうか。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
ログイン(会員の方はこちら)
無料会員登録
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け
この記事の特集
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら






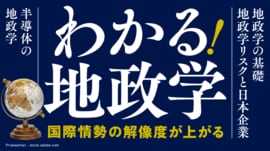










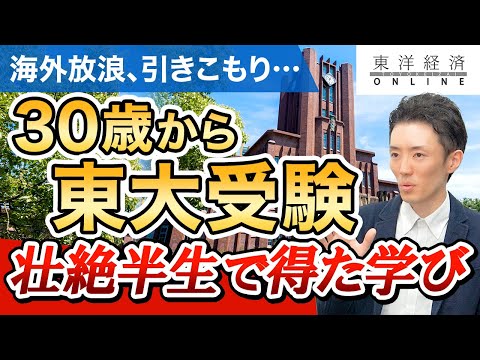











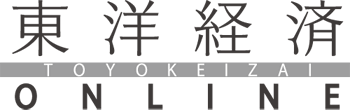


ログインはこちら