観念的な流行語が企業を惑わすことは少なくないが、近年では「経営と執行の分離」の右に出るものはなかろう。この要請は、どのように受け止めればよいのであろうか。経営と執行を分離せよと言われても、企業サイド…
この記事は有料会員限定です。
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら




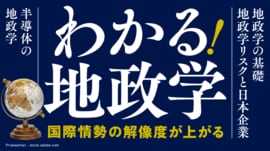










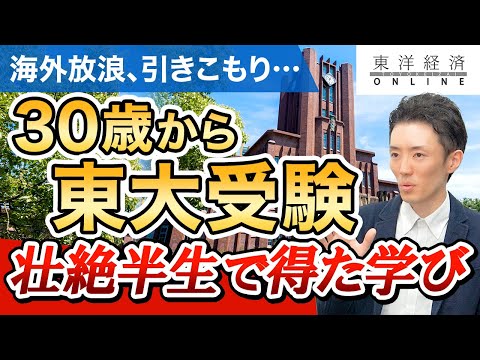



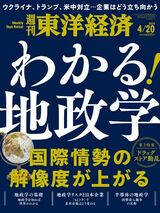







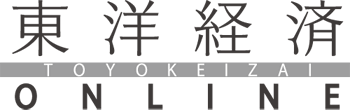


ログインはこちら