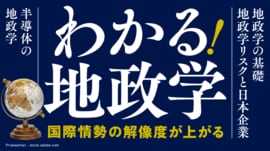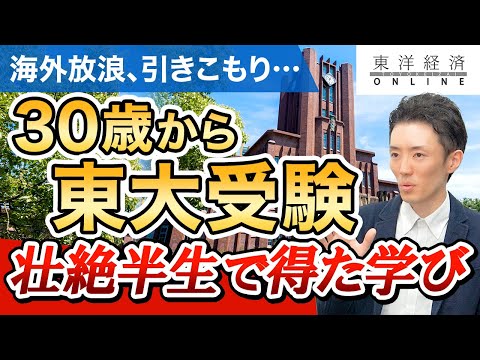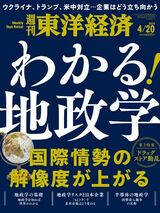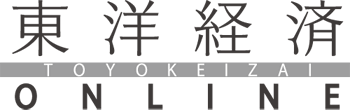非正規シフトの背景にある自営業の継続的減少
評者 BNPパリバ証券経済調査本部長 河野龍太郎
1990年代初頭に1割強だった非正規雇用比率は、今や3割を超える。多くの人は非正規雇用が増え正規雇用が減ったと考えるが、実は80年代から正規雇用は減っていない。いったい何が生じたのか。
本書は、気鋭の労働経済学者が丁寧なデータ分析を基に、労働市場全体の姿を俯瞰したものだ。非正規雇用増加の裏側で生じたのは自営業者の減少だった。非正規雇用比率の大幅上昇に目を奪われ、いつの間にか自営業者の継続的な減少と被用者の継続的な増加が忘れ去られていた。
日本的雇用慣行が崩壊したという通説にも反論する。長期雇用体系を見ても、年功賃金体系を見ても、データからは日本的雇用慣行のコア部分はほとんど変わっていないと結論する。労働需給の逼迫にもかかわらず、正規雇用の賃金上昇が鈍いのは、日本的雇用慣行が維持されているからと考えるべきなのだろう。
ただ、変化がまったくないわけではない。欧米と同様、雇用の二極化は生じた。賃金格差は拡大していないというのが通説だが、男性では拡大傾向にある。女性の格差が縮小しているため、男女合計で見ると格差が覆い隠されていたのだ。男性は、同一能力でも就業する事業所の違いで賃金格差が拡大するという興味深い現象が観測される。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待