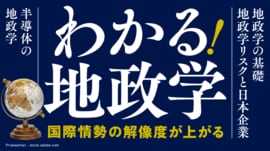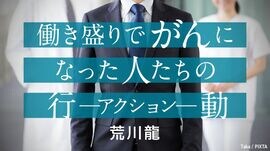ちゅう・にん●中国上海交通大学上海高級金融学院副院長。米イェール大学国際金融センター・ファカルティ・フェロー、米カリフォルニア大学特別任期金融論教授、北京大学光華管理学院特別任期金融論教授を経る。中国帰国前にカリフォルニア大学金融論終身教授に。
過大なリスクテイクの抑制にかかる
評者 BNPパリバ証券経済調査本部長 河野龍太郎
リーマンショック後に、誰もが想定したより早く、世界経済の回復が始まったのは中国が財政投融資策を発動し、GDP(国内総生産)の10%を超える高成長に回帰したからだ。しかし、ちょうど高度成長期が終わるタイミングだったため、無理な景気のかさ上げは、過剰ストックや過剰債務を生み、経済の大きな足かせとなった。
本書は、米国で長く研究を続けた中国人経済学者が、繰り返し生じる中国バブルの真因を探り、安定成長の条件を探ったものだ。
最大の問題は、世界金融危機の際、景気を急回復させるため、政府の暗黙の保証を強化したことだと論じる。破たんをさせないという暗黙の保証を信じ、国有銀行は返済を気にせず国有企業への融資を増やし、国有企業も生産能力を大幅に増強した。高度成長期が終わり、成長分野の発見に金融市場を活用すべきタイミングで、政府依存がより強化され、金融規律も失われた。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
ログイン(会員の方はこちら)
無料会員登録
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け
トピックボードAD
有料会員限定記事
連載一覧
連載一覧はこちら