日印原子力協定の危うさ 国会承認の過程で判明
原発輸出に前のめりの安倍政権。インドの核軍拡に利用されるおそれもある。

原発輸出に邁進するあまり、核軍拡を後押しすることになりはしまいか──。
日本政府がインドと昨年11月に結んだ原子力協定の国会承認手続きが進む中、核問題に詳しい専門家から、懸念の声が上がっている。
原子力協定とは、核物質や原子炉などの原子力関連資機材・技術を輸出する際に、輸入国が平和的に利用するよう求める法的な枠組みだ。日本はこれまで米国や中国など14の国および地域と協定を締結している。
ただインドとの協定締結は簡単ではない。同国が核不拡散条約(NPT)に非加盟で、軍縮や核不拡散の法的義務を負わないためだ。
政府の原子力委員会で委員長代理を務めた長崎大学核兵器廃絶研究センターの鈴木達治郎教授は、日本が提供した設備を用いてのウラン濃縮や使用済み核燃料の再処理を認めている点を問題視する。
「インドは1998年に2度目の核実験を強行して以来、核弾頭の数を増やしてきた。設備を提供してウラン濃縮や再処理を認めることは、民生用であるとはいえ、核兵器の材料となりうる核物質の保有量を増やす手助けになりかねない」
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待

![[INTERVIEW]ロバート・ガルーチ](https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/a/6/200w/img_a6a059ef8496706f16d2cae89834ece945189.jpg)



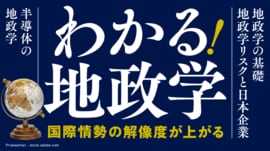





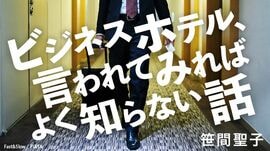
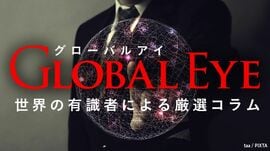







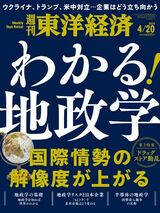







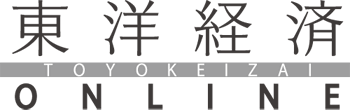


ログインはこちら